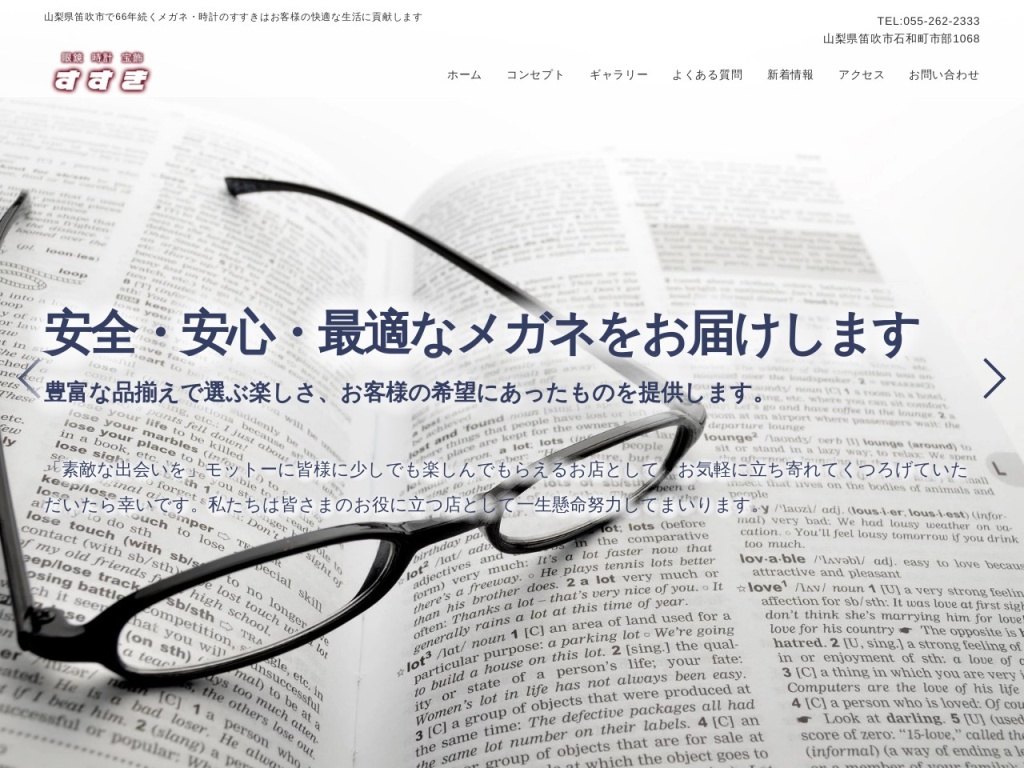「インシデント対応が特定の担当者に依存し、その人がいないと業務が止まってしまう…」。そんな「属人化」の問題にお悩みではありませんか。インシデント管理の属人化は、対応の遅延やサービス品質の低下を招く重大な経営リスクです。この記事では、インシデント管理の基本的な定義から、属人化を防ぐための具体的な解決策を網羅的に解説します。誰でも同じ品質で対応できる「標準フローの6ステップ」と、それを組織に定着させるための「3つのポイント」を詳述。さらに、Jira Service Managementなど国内で実績のあるツールの選定ポイントまでご紹介します。本記事を読めば、貴社のインシデント対応プロセスを標準化し、安定したサービス運用を実現する道筋が見えるはずです。
インシデント管理とは何か その目的と重要性
ITシステムがビジネスの根幹をなす現代において、「インシデント管理」は企業活動を安定的に継続させるための生命線とも言える重要なプロセスです。しかし、その言葉の意味や目的を正しく理解できているでしょうか。本章では、インシデント管理の基本的な定義から、なぜ今ビジネスに不可欠とされるのか、そして混同されがちな「問題管理」との違いまでを分かりやすく解説します。
インシデント管理の基本的な定義
インシデント管理とは、ITサービスの予期せぬ中断や品質の低下(これらを「インシデント」と呼びます)が発生した際に、可能な限り迅速にサービスを正常な状態に復旧させ、ビジネスへの影響を最小限に抑えるための一連のプロセスのことです。例えば、「Webサイトが表示されない」「社内システムにログインできない」「メールが送受信できない」といった事象がインシデントにあたります。
世界的に利用されているITサービスマネジメントのフレームワーク「ITIL(Information Technology Infrastructure Library)」においても、インシデント管理は中心的なプロセスとして位置づけられています。その最大の目的は、根本原因の追及よりも、まずはサービスを復旧させる「応急処置」を優先することにあります。
なぜ今インシデント管理がビジネスに不可欠なのか
DX(デジタルトランスフォーメーション)が加速し、あらゆる業務がITシステムに依存する現在、システムの停止は単なる「不便」では済まされません。それは直接的な売上機会の損失、生産性の低下、そして顧客からの信頼失墜につながる、重大な経営リスクとなります。
例えば、ECサイトが1時間停止すればその間の売上はゼロになり、顧客は競合サイトへ流れてしまうかもしれません。また、社内の基幹システムが停止すれば、全社員の業務がストップし、多大な人件費が無駄になる可能性もあります。このように、インシデント管理は、ビジネスの継続性と顧客からの信頼を維持し、企業価値を守るために不可欠な活動なのです。
インシデント管理と問題管理の違い
インシデント管理とよく混同される言葉に「問題管理」があります。両者は密接に関連していますが、その目的と役割は明確に異なります。インシデント管理が「今起きている火事を消す」応急処置であるのに対し、問題管理は「火事の原因(火元)を特定し、二度と火事が起きないようにする」再発防止策と言えます。
この2つのプロセスの違いを理解することは、効果的なインシデント管理体制を構築する上で非常に重要です。以下の表で、それぞれの目的や活動内容の違いを確認しましょう。
| 比較項目 | インシデント管理 | 問題管理 |
|---|---|---|
| 目的(ゴール) | サービスの迅速な復旧とビジネス影響の最小化 | インシデントの根本原因の特定と恒久的な解決による再発防止 |
| 時間軸 | 短期的・緊急(今すぐ対応) | 中長期的・計画的(原因をじっくり調査) |
| 主な活動 | 影響範囲の特定、回避策の適用、エスカレーション、復旧作業 | 根本原因分析(RCA)、恒久的な解決策の立案・実装、ナレッジの蓄積 |
| KPIの例 | 平均解決時間(MTTR)、初回コール解決率 | インシデント発生件数の削減率、既知のインシデント数 |
効果的な運用のためには、まずインシデント管理プロセスで迅速にサービスを復旧させた後、そのインシデントが繰り返し発生するようであれば問題管理プロセスに引き継ぎ、根本原因を解決するという連携が不可欠です。
インシデント管理の属人化が引き起こす3つの経営リスク
インシデント管理のプロセスが特定の従業員のスキルや経験に依存する「属人化」は、多くの組織が抱える深刻な課題です。一見、優秀な担当者によって業務が円滑に進んでいるように見えても、その裏ではビジネスの根幹を揺るがしかねない大きなリスクが潜んでいます。ここでは、インシデント管理の属人化が引き起こす具体的な3つの経営リスクについて詳しく解説します。
対応の遅延とサービス品質の低下
属人化の最も直接的な影響は、インシデント対応の遅れです。特定の担当者しか対応方法やシステムの仕様を把握していない場合、その担当者が休暇や会議などで不在の際にインシデントが発生すると、初動が大幅に遅れてしまいます。結果として、システムのダウンタイムが長引き、顧客満足度の低下やビジネス機会の損失に直結します。
特にSLA(Service Level Agreement)でサービス品質を保証している場合、対応の遅延は契約違反となり、ペナルティの発生や信用の失墜といった金銭的・ブランド的な損害につながる可能性も否定できません。迅速性が求められるインシデント対応において、担当者一人に依存する体制は、極めて脆弱なボトルネックと言えるでしょう。
ノウハウが共有されず組織が停滞する
ベテラン担当者が長年の経験と勘を頼りにインシデントを解決するケースは少なくありません。しかし、その貴重な知識や手順がドキュメント化されず、個人の頭の中にしか存在しない場合、それは組織の資産にはなりません。他のメンバーは同様のインシデントに直面しても効率的な解決策がわからず、毎回ゼロから調査を始める非効率な状況が続いてしまいます。
これにより、チーム全体のスキルレベルが底上げされず、組織としての問題解決能力が向上しません。個人のファインプレーに頼る組織は、再現性がなく、持続的な成長が見込めないのです。ナレッジが共有されない文化は、新メンバーの教育コスト増大にもつながり、組織全体の停滞を招きます。
担当者の退職による業務ブラックボックス化
属人化がもたらす最大のリスクは、キーパーソンとなる担当者の退職や異動です。その担当者がいなくなった途端、誰もインシデントの対応方法がわからなくなり、最悪の場合、業務が完全に停止してしまう恐れがあります。
引き継ぎが不十分なまま担当者が去ってしまうと、システムの複雑な設定や過去の対応経緯、独自の運用ルールなどがすべて失われ、残された業務は「ブラックボックス」と化します。システムの仕様や運用ノウハウが個人に紐づく状態は、事業継続計画(BCP)の観点からも極めて危険です。一度ブラックボックス化してしまうと、新たなインシデントの原因究明が困難になるだけでなく、将来的なシステムの改修や改善もままならなくなります。
| ブラックボックス化の要因 | 具体的なビジネスインパクト |
|---|---|
| 担当者の急な退職・異動 | 業務プロセスの停止、システムの復旧不能 |
| ドキュメント化されていない運用手順 | 軽微なトラブルが重大インシデントに発展 |
| 引き継ぎの失敗 | 原因調査に膨大な時間を要し、機会損失が増大 |
| 個人にしか分からない設定情報 | セキュリティ脆弱性の放置、システム改修の断念 |
属人化を防ぐインシデント管理の標準フロー6ステップ
インシデント管理の属人化を防ぎ、誰が対応しても一定の品質を担保するためには、対応フローの標準化が不可欠です。ここでは、ITIL(Information Technology Infrastructure Library)などの国際的なベストプラクティスを基にした、インシデント管理の標準的な6ステップを解説します。このフローを組織全体で徹底することが、迅速なサービス復旧と業務の安定化に繋がります。
ステップ1 インシデントの検知と記録
インシデント管理の最初のステップは、インシデントの発生を「検知」し、その内容を正確に「記録」することです。この入口のプロセスが曖昧だと、後の対応すべてに遅れや混乱が生じます。
インシデントの検知は、エンドユーザーからの報告(電話、メール、チャットツール)、システム監視ツールからの自動アラート、あるいは担当者が業務中に発見するなど、様々な経路で発生します。重要なのは、どのような経路で検知したインシデントであっても、必ず一元的に記録するルールを設けることです。
記録する際には、インシデント管理ツールやチケット管理システムを用いて、以下の情報を漏れなく入力します。
- 報告者の氏名・連絡先
- インシデントの発生日時
- 発生場所や対象システム
- 具体的な事象(エラーメッセージなど)
- 業務への影響範囲
これらの情報を正確に記録することで、対応の引き継ぎがスムーズになり、後の分析にも役立ちます。
ステップ2 カテゴリ分類と優先度付け
記録されたインシデントは、次に「カテゴリ分類」と「優先度付け」を行います。これにより、対応すべき担当チームが明確になり、限られたリソースを最も重要なインシデントに集中させることができます。
カテゴリ分類は、「ハードウェア障害」「ソフトウェアのバグ」「ネットワーク接続の問題」「アカウント関連の問い合わせ」のように、あらかじめ定義された分類項目に従って行います。適切な分類は、担当者の割り振りや、将来的な傾向分析に不可欠です。
優先度付けは、インシデントがビジネスに与える「影響度」と、対応を要する「緊急度」の2つの軸を組み合わせて決定するのが一般的です。以下の優先度決定マトリクスを参考に、自社の状況に合わせた基準を設けましょう。
| 緊急度:高 (すぐに解決が必要) | 緊急度:中 (数日中に解決が必要) | 緊急度:低 (計画的な対応が可能) | |
|---|---|---|---|
| 影響度:高 (基幹システム停止など) | 最優先 | 高 | 中 |
| 影響度:中 (一部門の業務停止など) | 高 | 中 | 低 |
| 影響度:低 (個人PCの不具合など) | 中 | 低 | 低 |
客観的な基準に基づいて優先度を決定する仕組みが、担当者の判断によるバラつきを防ぎ、対応の公平性を保ちます。
ステップ3 初期調査と一次対応
優先度が決定したら、サービスデスクやヘルプデスクなどの一次対応チームが「初期調査」を開始します。ここでは、報告者へのヒアリングやシステムのログ確認などを通じて、インシデントに関するより詳細な情報を収集し、原因の切り分けを行います。
この段階で目指すべきは「FCR(First Call Resolution:一次解決率)」の向上です。過去のナレッジベースを検索し、既知の問題であれば、その場で解決策を提示します。例えば、パスワードのリセットや、簡単な設定変更などで解決できるケースがこれにあたります。
すぐに根本解決が難しい場合でも、業務への影響を最小限に抑えるための暫定的な回避策(ワークアラウンド)を提示することも、一次対応の重要な役割です。迅速な一次対応は、ユーザーの満足度を大きく左右します。
ステップ4 専門チームへのエスカレーション
一次対応チームで解決できないインシデントは、より専門的な知識や権限を持つ二次・三次対応チームへ「エスカレーション(引き継ぎ)」します。
エスカレーションには、より高度な技術スキルを持つチームへ引き継ぐ「機能的エスカレーション」と、上位の管理者へ承認や判断を仰ぐ「階層的エスカレーション」があります。誰が、どのような場合に、どこへエスカレーションするのか、ルールを明確に定めておくことが重要です。
エスカレーションを成功させるための鍵は、情報共有です。ステップ1で記録した内容や、ステップ3での初期調査の結果、試した対応などをすべて正確に伝えることで、引き継ぎ先での重複した調査を防ぎ、解決までの時間を大幅に短縮できます。インシデント管理ツールに対応履歴をすべて記録しておくことが、スムーズなエスカレーションを実現します。
ステップ5 インシデントの解決と復旧
エスカレーションを受けた専門チームは、インシデントの根本原因を特定し、解決策を策定・実行します。これには、システムの修正、設定の変更、ハードウェアの交換などが含まれます。
解決策を適用した後は、必ず「復旧確認」を行います。システムが正常に動作することを確認し、インシデントを報告したユーザーにも実際に利用してもらい、問題が解消されたことを確認します。この確認作業を怠ると、インシデントが再発したり、別の問題を引き起こしたりする可能性があります。
対応は、SLA(Service Level Agreement:サービス品質保証)で定められた目標復旧時間内に完了させることを目指します。時間を意識した対応が、ビジネスへの影響を最小限に食い止めます。
ステップ6 クローズとナレッジ化
インシデントが解決し、ユーザーからの同意も得られたら、チケットを「クローズ」します。しかし、ここで業務を終わりにしてはいけません。属人化を防ぐためには、最後の「ナレッジ化」が最も重要なステップです。
今回のインシデント対応の全記録(発生事象、原因、調査プロセス、最終的な解決策など)を整理し、誰もが検索・参照できる「ナレッジベース」に登録します。このナレッジの蓄積こそが、組織全体の財産となります。
対応プロセスを形式知として蓄積することで、将来同じインシデントが発生した際に、担当者が変わっても迅速かつ的確に対応できるようになります。また、影響の大きかったインシデントについては、関係者で事後レビュー(PIR: Post Incident Review)を行い、再発防止策を検討し、「問題管理」のプロセスへと繋げていくことも有効です。
フロー標準化を実現するインシデント管理3つのポイント
インシデント管理の標準フローを確立しても、それを「誰が」「どのような基準で」「どのように」実行するのかが曖昧では、結局は個人のスキルや経験に依存してしまい、属人化を防ぐことはできません。ここでは、定義したフローを組織全体で安定して運用するための、具体的な3つのポイントを解説します。
対応ルールの明確化とドキュメント整備
インシデント対応における判断基準や手順を明文化し、誰でもアクセスできる場所にドキュメントとして整備することが、標準化の第一歩です。担当者の勘や経験に頼るのではなく、定められたルールに基づいて行動することで、対応の質を均一化し、迅速な意思決定を支援します。特に重要なのが「優先度決定」と「エスカレーション」のルールです。
優先度決定マトリクスを定める
インシデントが発生した際、最初に行うべきは対応の優先度付けです。しかし、この判断が担当者によって異なると、本来であれば最優先で対応すべき重大なインシデントが後回しにされてしまうリスクがあります。そこで、客観的な基準として「優先度決定マトリクス」を定義します。一般的には「ビジネスへの影響範囲」と「緊急度」の2つの軸で評価します。
| 影響範囲:大(全社的なシステム停止など) | 影響範囲:中(特定部門の業務遅延など) | 影響範囲:小(個人単位の軽微な問題など) | |
|---|---|---|---|
| 緊急度:高(即時対応が必要) | 最優先 | 高 | 中 |
| 緊急度:中(計画的な対応が可能) | 高 | 中 | 低 |
| 緊急度:低(業務時間内の対応で可) | 中 | 低 | 低 |
このようなマトリクスを用意することで、誰がインシデントを受け付けても、一貫した基準で優先度を判断できるようになり、対応のブレをなくします。
エスカレーションルートを可視化する
一次対応者だけでは解決が困難なインシデントは、速やかに専門チームや上位の管理者へ報告・相談(エスカレーション)する必要があります。このエスカレーションの判断が遅れると、問題解決までの時間が長引き、ビジネスへの影響が拡大してしまいます。「どのような場合に」「誰に」「どのように」エスカレーションするのか、そのルートを明確に定義し、フローチャートなどで可視化しておくことが重要です。
例えば、「優先度が『最優先』または『高』のインシデントは、発生から15分以内に担当部署のリーダーに報告する」「特定のアプリケーションに関する問題は、〇〇部の開発チームへ引き継ぐ」といった具体的なルールを定めます。これにより、担当者が判断に迷う時間を削減し、組織として迅速かつ的確な対応が可能になります。
役割と責任範囲(RACI)を定義する
インシデント管理プロセスに関わるメンバーそれぞれの役割と責任を明確にすることも、属人化を防ぐ上で欠かせません。そのためのフレームワークとして「RACI(レイシー)チャート」が有効です。RACIは、以下の4つの役割の頭文字を取ったものです。
- R (Responsible): 実行責任者 – 担当タスクを実際に実行する人
- A (Accountable): 説明責任者 – 最終的な意思決定と結果に責任を持つ人(各タスクに1名のみ)
- C (Consulted): 協業先 – 専門的な知見を提供し、相談を受ける人(双方向のコミュニケーション)
- I (Informed): 報告先 – 進捗や結果の報告を受ける人(一方向のコミュニケーション)
インシデント管理の各プロセスにおいて、誰がどの役割を担うのかを一覧表にまとめることで、責任の所在が曖昧になるのを防ぎ、関係者間のスムーズな連携を促進します。
| プロセス | サービスデスク担当者 | 専門チームエンジニア | チームリーダー | 事業部長 |
|---|---|---|---|---|
| インシデントの記録 | R | I | A | I |
| 初期調査・一次対応 | R | C | A | I |
| 専門チームへのエスカレーション | R | A | I | I |
| インシデントの解決・復旧 | I | R | A | C |
| クローズと報告 | R | I | A | I |
このチャートにより、各担当者は自分が何をすべきか、誰に相談・報告すべきかを明確に理解でき、迷いなく行動できるようになります。
ナレッジベースを構築し活用する文化を醸成する
インシデント対応で得られた知見は、特定の担当者の中だけに留めておくのではなく、組織全体の資産として蓄積・共有することが極めて重要です。その仕組みが「ナレッジベース」です。過去に発生したインシデントの原因、対応手順、解決策などを記録しておくことで、類似のインシデントが発生した際に、誰もが迅速かつ効果的な対応を取れるようになります。
効果的なナレッジベースを構築・運用するためには、以下の点がポイントとなります。
- 記録フォーマットの統一: 「発生日時」「事象」「影響範囲」「原因調査」「暫定対応」「恒久対策」といった項目をテンプレート化し、誰が書いても分かりやすい記録を目指します。
- 検索性の向上: インシデントのカテゴリや関連システム名などでタグ付けを行い、必要な情報をすぐに見つけ出せるようにします。
- 情報の鮮度の維持: 定期的にナレッジを棚卸しし、古い情報や誤った記述を更新するプロセスを設けます。
ただし、最も重要なのはツールを導入すること以上に、ナレッジを記録し、参照する文化を組織に根付かせることです。インシデント対応完了後のナレッジ登録をフローに組み込んだり、有益なナレッジを共有したチームを表彰したりするなど、全員が情報共有の価値を理解し、積極的に活用する風土を醸成していくことが成功の鍵となります。
失敗しないインシデント管理ツールの選定ポイントとおすすめツール
インシデント管理のフローを標準化し、属人化を解消するためには、インシデント管理ツールの導入が極めて効果的です。Excelやスプレッドシートによる手動管理では、リアルタイムでの情報共有や対応履歴の追跡が難しく、結果的に特定の担当者に負荷が集中する原因となります。適切なツールを選定することで、インシデント対応のプロセスを可視化し、組織全体の対応力を底上げできます。
しかし、多機能なツールが必ずしも自社に最適とは限りません。本章では、自社の課題を解決し、インシデント管理を成功に導くためのツールの選定ポイントと、国内で広く利用されているおすすめのツールを具体的に解説します。
インシデント管理ツール選定で比較すべき項目
インシデント管理ツールを選定する際は、単に機能の多さや価格だけで判断するのではなく、自社の状況や目的に照らし合わせて多角的に比較検討することが重要です。ここでは、特に重視すべき3つの比較項目を解説します。
自社の規模と目的に合っているか
まず考慮すべきは、ツールの機能や価格体系が自社の規模やインシデント管理を行う目的に合致しているかという点です。例えば、数名のIT担当者で社内からの問い合わせに対応するケースと、大規模な開発チームとSREチームが連携してサービス障害に対応するケースでは、求められる機能が大きく異なります。
小規模なチームであれば、シンプルで直感的に使える操作性と、導入コストを抑えられるツールが適しています。一方、大規模な組織やITILに準拠した本格的なITサービスマネジメント(ITSM)を目指す場合は、ワークフローのカスタマイズ性や承認プロセス、SLA(サービスレベル合意)管理機能などが充実しているツールが必要になります。自社の現状と将来の展望を見据え、過不足のないツールを選びましょう。
外部サービスとの連携は容易か
インシデント管理は、単独の業務で完結することは稀です。日々の業務で利用しているチャットツールやバージョン管理システム、監視ツールなど、様々な外部サービスと連携できるかどうかは、業務効率を左右する重要なポイントです。
例えば、以下のような連携が可能かを確認しましょう。
- チャットツール連携:SlackやMicrosoft Teamsなどにインシデント発生の通知を自動で送り、ツール上でチケットを作成できるか。
- 監視ツール連携:DatadogやZabbixなどの監視ツールが異常を検知した際に、自動でインシデントを起票できるか。
- 開発ツール連携:GitHubやGitLabなどのバージョン管理システムと連携し、インシデントの原因となったコードの特定や修正をスムーズに行えるか。
APIが公開されており、柔軟な連携が可能か、あるいは標準で連携できるサービスの数(エコシステム)が豊富かという視点で確認することで、導入後のスムーズな運用に繋がります。
レポート機能は充実しているか
インシデント管理の目的は、単に発生した事象を解決するだけではありません。蓄積されたデータを分析し、サービス品質の改善や将来のインシデント発生を予防することも非常に重要です。そのため、レポート機能の充実度は必ず確認すべき項目です。
具体的には、以下のような項目を可視化できるかを確認しましょう。
- インシデントの発生件数や傾向
- 対応時間や解決までの時間(MTTR)
- SLAの遵守率
- 担当者やチームごとの対応状況
これらのデータをダッシュボードでリアルタイムに把握できたり、定期的にレポートとして自動出力できたりする機能があれば、ボトルネックの特定や改善活動に大いに役立ちます。
国内で人気のインシデント管理ツール3選
ここでは、前述した選定ポイントを踏まえ、国内の多くの企業で導入実績のある代表的なインシデント管理ツールを3つご紹介します。それぞれのツールの特徴を比較し、自社に最適なツールを見つけるための参考にしてください。
| ツール名 | 主な特徴 | 向いている企業・チーム |
|---|---|---|
| Jira Service Management | ITIL準拠の本格的なITSM機能。開発ツールJira Softwareとの親和性が非常に高い。自動化ルールやカスタマイズ性に優れる。 | 開発部門とIT運用部門の連携を強化したい企業。中規模から大規模な組織。 |
| Redmine | オープンソースで無償利用可能(※)。プラグインによる高い拡張性。インシデント管理以外にタスク管理やプロジェクト管理にも活用できる。 | コストを抑えたい企業。自社でサーバーを構築・運用できる技術力がある企業。柔軟なカスタマイズを求める企業。 |
| Backlog | 国産ツールならではの直感的なUI。非エンジニアでも使いやすいシンプルな操作性。プロジェクト管理機能が充実。 | 初めてツールを導入する企業。IT部門だけでなく全社的に利用したい企業。小規模から中規模のチーム。 |
Jira Service Management
Jira Service Managementは、アトラシアン社が提供するITサービスマネジメント(ITSM)ツールです。開発プロジェクト管理ツールとして世界的に有名なJira Softwareとシームレスに連携できる点が最大の特徴です。開発チームが利用するチケットとIT運用チームが管理するインシデントを一元管理できるため、DevOpsを推進し、開発から運用までのプロセスを円滑にしたい企業に最適です。ITILフレームワークに準拠したテンプレートが用意されており、本格的なインシデント管理、問題管理、変更管理のプロセスを構築できます。
Redmine
Redmineは、オープンソースのプロジェクト管理ソフトウェアであり、インシデント管理ツールとしても広く利用されています。最大のメリットは、自社のサーバーにインストールすればライセンス費用がかからず無償で利用できる点です。豊富なプラグインを導入することで、自社の業務フローに合わせて機能を柔軟に拡張できます。一方で、サーバーの構築やメンテナンス、セキュリティ対策などを自社で行う必要があるため、ある程度の技術力が求められます。コストを抑えつつ、自社の要件に合わせて自由にカスタマイズしたい場合に有力な選択肢となります。
Backlog
Backlogは、福岡に本社を置く株式会社ヌーラボが開発・提供する国産のプロジェクト管理・タスク管理ツールです。そのシンプルで直感的なインターフェースは、IT部門の専門家だけでなく、企画、マーケティング、総務といった非エンジニアのメンバーでも迷わずに使えるように設計されています。インシデントを「課題」として登録し、担当者や期限を設定して進捗を管理する、という分かりやすい運用が可能です。日本語のサポートも手厚く、初めてインシデント管理ツールを導入する企業や、IT部門以外のチームも巻き込んで全社的に情報共有を進めたい場合に適しています。
まとめ
本記事では、インシデント管理の属人化が引き起こす経営リスクと、それを防ぐための具体的な手法について解説しました。インシデントへの迅速かつ的確な対応は、サービスの安定稼働と顧客信頼の維持に直結する、現代ビジネスの生命線です。
属人化を防ぐための結論は、「インシデント管理プロセスの標準化」と「適切なツールの活用」に集約されます。「検知・記録」から「解決・ナレッジ化」までの一貫したフローを定め、優先度マトリクスや責任範囲(RACI)を明確にすることで、担当者個人のスキルに依存しない、組織的な対応が可能になります。
Jira Service Managementのようなツールは、標準化されたフローの実行を強力に支援しますが、自社の規模や目的に合致したものを選ぶことが成功の鍵です。本記事で紹介したステップとポイントを参考に、属人化のリスクを排除し、組織全体の資産となる強固なインシデント管理体制を構築してください。
【PR】関連サイト
SHERPA SUITE
〒108-0073東京都港区三田1-2-22 東洋ビル
URL:https://www.sherpasuite.net/